禅フォトギャラリー ブックレヴュー
禅フォトギャラリーは、2009年9月にマーク・ピアソンによって設立された、アジア諸国の写真を専門的に紹介するギャラリーです。展覧会の開催のみならず、写真集の出版を活発に行っており、刺激的な写真作品を継続して提示しています。今年で記念すべき10周年を迎える禅フォトギャラリーがこれまでに刊行した出版物を再俯瞰する、ブックレヴューページを特設しました。(レヴューは随時更新され、掲載タイトルが増える予定です。)
『¥€$U$ (イエス)』 Pawel JASZCZUK
自由とは?
ポーランドの写真家、パヴェウ・ヤシュチュク。
2008年から2010年の間に酔態し、路上で寝込むサラリーマンを撮影したシリーズ“ハイファッション”は、日本でも大きく話題を呼んだ。
パヴェウは、約10年間のオーストラリアと日本での海外生活を終え、2012年にポーランドに帰国した。その際、母国の「民間信仰」に再び遭遇した。
イエス。
人の性をとった神。キリスト教の中心人物。多くのキリスト教徒に、イエスは神の子であり神と本質を同じくすると理解されている。
新約聖書のキリストと、現代大衆文化で表現されている“イエス”
乖離する“イエス”の存在定義。
この、宗教的価値観と商業主義的価値観で現される“イエス”にパヴェウは、大きなカルチャーショックを受ける。
日本でも、宗教観ではなく、商業的にICONIQな存在として世の中に浸透している。
その存在は、信仰や、聖なるイメージからは、遥か遠いところにある。
信仰は、人を救い、人が生きて行く上で必要であると理解する。
しかし、自由とは何だろうか?
パヴェウが提起する“イエス”も、今世に生きる人々が創り出したイメージであり、人が人を不自由にしている“様”を捉えているようようにも思える。
その点において、パヴェウの写真は、常に人が創り出した、今世の観念への問いであり、写真でしか提起出来ない問題を具現化している。
パヴェウの“イエス”から、今一度、自由を問われる、クリスマスとなった。
― Jeong Imhyang

『The Hunter Gets Captured By The Game』 Chris SHAW
イギリス人の写真家、クリス・ショウ。
“ライフ・アズ・ナイトポーター”は、彼の最も有名なシリーズである。
写真を大学で学んでいたクリスは、ただのお金持ちの退屈しのぎに大学へ通う彼等を避け、サンディー・ヒル団地に入り浸る様になる。
芸術と日常の狭間で、いつしか、混沌と過ぎ去る人々の、現実の中に起こる“アンリアル”にクリスの視線は向けられて行き、ホテルのボーイとして働いていた時期に撮影された“ライフ・アズ・ナイトポーター”で、クリス写真にしか見当たらない、現実の中の“アンリアル”を確立した。
本作の舞台は、タイのパタヤである。
レディーボーイ、ゴーゴーバー、売春婦。
昼か夜かも分からない程に、背徳を覆い尽くす快楽と歓楽。
クリスの“アンリアル”は、底なき人間の混濁した欲望へと向かう。
本タイトルになっている“The Hunter Gets Captured By The Game”は、1966年に、Smokey Robinsonによって制作されリリースされたソウルナンバーである。
クリスの手法で焼かれた写真には、人間の欲望が騒めき、湯立つ様な業が、定着させられている。
“あなたのために罠をかけたが、捕まったようだ”
人間の欲望ほど、恐ろしいものはない。
クリスはその欲望に触れる寸前で、シャッターを切る。
“そこ”に、本当に触れると、後戻りは出来ない。
“そこ”に住む人々と、戻って行く他者である己。
クリスは、わざと罠をかけ、捕まったのではないかと思う。
“そこ”に住む人々への悲哀と尊厳を抱きながら。
― Jeong Imhyang

『SEKAINOHEIWA/TSUMITOBATSU/AKARUIMIRAI』 マツモトダイスケ
正義とは?
マツモトダイスケによる、セットアップで構成撮影された、メタフィクション。
ウルトラマン、怪獣、猿。
マツモト写真に登場するのは、小学生にも伝わる登場人物である。
マツモトが掲げる”正義”を、薄めて薄めて誰にでも分かる形で現わしたのが、メタフィクションという手法だったのではないだろうか。
マツモト写真が起こす物語には、必ず暴力が起きる。
その暴力をどう解釈するかを、視る者に問い、そして、その暴力性への”答え”もまた、視る者に委ねられる。
私はこの"答え"を、子供に問いたいという思いに駆られる。
日本の教育は、芸術において他国に比べ、不自由な環境にあると私は思う。小学生から芸術に今以上に、触れられる環境があってもいいのではないか。
無論、芸術は教育されるものではない。
しかし、真っ白な脳の幼少期に、視て、触れたものに人間が影響を受ける事は事実である。
マツモト写真が提起する”正義”は、凝り固まった大人の脳には期待せず、子供の方が明確な”答え”を出せるという皮肉と、それと同時に、現代社会が創り出す正義への反逆でもある様に思う。
マツモトの写真集だけでなく、芸術ともっと広く五感に触れることが出来る教育の時間を、日本の子供達が持つ事が出来る事を願い、そして、芸術が当たり前の日常として存在する世になる事が”AKARUIMIRAI”となるのではないだろうか。
― Jeong Imhyang

『東大1968-1969ー封鎖の内側』 渡辺眸
日本の写真家を代表する一人である渡辺眸。
戦後の日本の文化の拠点である新宿を撮り射抜いた、”新宿コンテンポラリー”は、今や伝説的写真集となっている。
その新宿で遭遇した”国際反戦デー”のデモ。
日本の学生の闘争の巨大なうねりが、群衆のひとりとして渡辺にリアリティを持たせ、渡辺の目線を、東大闘争へと向かわせた。
東大本郷キャンパスで、山本義隆(当時東大全共闘代表)に出会い、インスパイアーされた渡辺は、東大安田講堂のバリケード内で唯一撮影を許可された。
バリケード内の、生々しいまでの熱。
50年経つ今でも、渡辺写真にその純潔たる熱が未だ焼き付けられている。
その熱は、学生運動と時代が集約された闘争の証拠でもあるが、焼き付けられた熱の中に、何故か恋文の様な蕩めきを感じるのである。
写真の前では、男も女も違いはない。
ただの人間である。
しかし、誤解を恐れずに記すならば、女は女性性からは逃れられないという事を、渡辺写真から私は、今一度思い知ることになった。
そして、自分と他人は騙せても、写真は騙せないという事も。
ただの私の奥読みかもしれない。
それでも、渡辺写真に隠されたこの恋文を感じる事が出来る事が、女として生きている証であると、心を撫でられた様に思う。
妄想であったとしても、この写真集に出会えたことに謝辞を述べたい。
― Jeong Imhyang

『日々の川』平良博義
Zen Foto Galleryにて2016年に、山本雅紀×平良博議×瀬頭順平によって3人展が開催された。
キュレーションは写真家の布施直樹。
方向性もアプローチも違う3人だったが、モノクロームで撮り収められた写真からは、「生身の人々の声、その時の写真家と人々との関係、感情を肌で感じ取れる」
と、布施がコメントを寄せているように、撮る者と撮られる者との関係性が色濃く視覚に定着する3人展となった。
本書は、その中の一人である平良が、荒川に“住む”人々との日々を撮り収めた写真群である。
川の流れに添うように、過ぎ行く老人達の時間。
その時間は、とても穏やかで静かな生の紡ぎ。
路上の生活を撮り収めた写真は幾多とあるが、平良の写真には音がない。
静かに、荒さぬよう、そこに住む人々を見続け、幾度となく足を運び、語り合ったであろう日々が見え、平良の人となりを思う。
無音の写真からは、老人の柔かな語りだけが聞こえてくる。
「寒くねえか?」
「腹減ってねえか?」
「おめえ、また来たのか?」
平良写真から聞こえてくる、その柔らかな語りと、川の風景とが、老人達のここまでの道のりを思わせる。
撮り斬るのではなく“撮り受ける”視線。
優しすぎると、牙を剥かれるのが写真である。
その牙に負けぬよう、平良の視線でこの川と人々を見続けて欲しいと切に思う。
― Jeong Imhyang

『私の惨めな小宇宙への狂詩曲』韓超
言葉のない言葉。
2005年から2010年に、中国人である韓超によってカラーで撮り収められた、ダークポップな日常写真。そのカラーは、とろみのある湿度を纏い、その生ぬるい熱が視覚から肌を這う。
若い命と、生の艶かしさ。
中国の色彩が放つ美。
日常の中で、通り過ぎる家族と誰か。
死を予感させる花。
魂の愛撫と”boyfriends”
自身の真実の内界と、外界とを繋ぐ甘美で哀切なる写真。
繋がることの哀切さと、その哀切を傍観するような韓の視線。
どこか影を帯びたその視線には、中国において、ゲイである事をカミングアウトし、作家として生きていく事の厳しさと、韓を取り巻く環境への静観が見える。
その静観が、韓の写感を生み、写真でしか見ることが出来ない情感を生んでいる。
私は初恋を思い出した。
本当に心から人を好きになった日の事を。
人の心に触れる幸福と絶望。
その感情に言葉はない。
人の営みは単純で複雑だ。
韓の写真には、その”言葉ではない言葉”が存在し、五感を痛切に打ち、その余韻が、狂詩曲を奏でていく。
― Jeong Imhyang
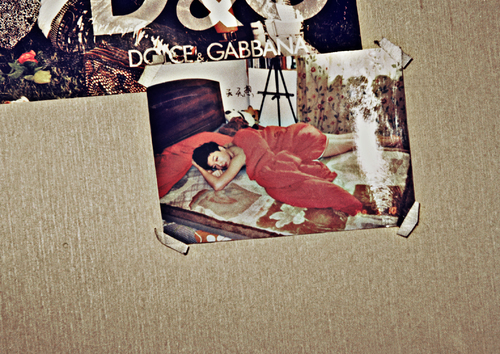
『星霜連関』下平竜矢
目に見えぬもの。
本書は、下平が日本各地の祭りや、聖地とされる場所などを、10年間かけて撮り収めた写真群である。
ある期間移り住んだ青森県八戸市から、三重県伊勢市。日本各地へ移動し、その土地の地場や、地霊との瞬間的交感を持って、撮影に挑んだ下平。
信仰に基づき、その土地土地で伝承されてきた祭り。
豊穣、感謝、祈り。
本書の撮影のきっかけとなった、青森県八戸市での古い神社での獅子舞の踊りを見た下平は、タイムスリップしたように原始の時間へ戻ったように感じたという。
私自身も、幼き頃に同じような体験をしたことがある。
現実と非現実の狭間で、その空間だけが時間軸に浮かんでいる様な、自己の肉体だけではなく、果てしない時空に何体もの体を通して、その光景を見ている様な、不可思議な記憶として、今も残像している。
その感覚を言葉で現すならば“血”である。
血が騒めき、蠢き、沸き立つ。
肉体も土地も滅びれば、全ては無になるだけだ。
しかし、もし魂という存在が人と土地にあるとするならば、その不可思議な血の感覚は、魂の記憶なのではないだろうか。
祈りという目に見えぬ魂。
下平のモノクロームには、その見えぬ人と土地の、魂の記憶が写り込んでいるように思う。
― Jeong Imhyang

『いずく』マキ
写真の輪廻。
本書は、フランス人であるMakiによって、2001年から2015年にかけて日本を旅した際に撮り収められた、モノクロームの写真群である。
輪廻があるとするならば、写真もまた、輪廻の旅なのか。
Japanese photographyに写る、独特の“気配”。
それは、日本人の潜在意識の中に宿っている、土着的な神仏習合であり、アニミズムである。日本人が持つ、その潜在意識は、テクノロジーが発展を遂げた現代でも変わる事なく継承され、その潜在意識を一言で現すならば日本人の“質”である。
その“質”は、日本芸術の中でも、写真の中にだけ色濃く現れる“質”があり、写真を物として捉えるならば、土着的な日本のアニミズムの賜物であると私は思う。
念写という言葉が日本ではあるように、日本写真にはどこか、念がついて回る。
その念を、フランス人であるMakiの写真からは感じられ、写真の輪廻を考察させられる。
日本人の念は、少し日本を旅した程度で宿るものではない。
ジャズやブルース、ソウルを生み出したブラックミュージック。レゲエ、バチャータ、サルサのラテンミュージック。先人が生きた歴史の痕跡として生み出し、継承し、輪廻する音楽は、今や、国籍に限らず、多種様々な人々がその音楽を愛し、奏でている。
Makiの写真からは、日本写真も同様に、世界でJapanese photographyというジャンルを確立させ、写真を輪廻させていることを改めて思わされる。
そして、その輪廻はまた日本に還り、Makiが魅せたように、新たなJapanese photographyとして、日本に“いづく”のであろう。
― Jeong Imhyang

『A Bastard Son』Brian SERGIO
本作は、フィリピン・マニラ出身の写真家ブライアン・セルジオの視線を通して撮り収められた、フィリピンの無法地帯のストリートスナップである。
街の喧騒、お腹を大きくした若い女性、路上の子供達、刺青の男、ゴーゴーバー。
“生きる為”の街。
欲と生がなまめかしく街を這う中、セルジオの視線は路上で生きる子供、ストリートチルドレンに近づいていく。
性ビジネスは立派なビジネスである。
需要と供給が明白に理に適っている。
宗教上、金銭的、或いは宿ってしまった母性などの理由により、産み落とされた生。
これは、フィリピンに限らず日本とて他人事ではない。
日本の様に、雨後の筍のように、どの街にも性風俗が満映している国は珍しい。
日本では、性風俗としてビジネスが成立しているにも関わらず、認可のある低容量ピルは諸外国より高額。緊急避妊薬も日本では未だ処方箋が必要な上、1.5万円前後と高額のままである。
中絶手術においても、母体に負担の少ない中絶薬には認可がなく、未だ掻爬法。
WHOが安全でない方法としている掻き出す術式である。
それとは反対に、勃起不全治療薬バイアグラは異例の速さで認可されている。
ニュースを見れば、児童の悲しいニュースを見ない日はない。
誤解なきよう理解頂きたいのは、悲しいニュース、ストリートチルドレンの原因が、女性が性ビジネスにおいて招いた事ではない。
恋愛においても、性ビジネスにおいても、宿る可能性がある生において、国が取る措置として、男性と女性の因果関係なるこの性ビジネスの縮図が、一番分かりやすいのである。
忘れてはいけないのは、そこには常に男性の存在があるという事だ。
恋愛をして、好きになって、愛する人の子供が欲しいと願うのは女性の本能である。
その上で、願っても叶えられない生もあり、女性を守るためにも、悲しい生が宿る事なきよう女性が選択出来る未来を、今一度考察すべきであり、セルジオの問いは国際的課題であると私は思う。
平等などなく、不条理が当たり前のこの世。
しかし、その当たり前が産み出した”様”が毎日流れる悲しいニュースであるのだ。
― Jeong Imhyang

『LET ME OUT』菱沼勇夫
馬の頭、血の裸体、凶器、三角のモチーフ。血族を思わせる男。マスク。
本作は、菱沼による世と自身の内面と外面の、相違から起こるイメージを具現化したカラーで撮り収められた、セットアップの写真群である。
撮り収められた“物”は、菱沼による造形物であり、リアルとアンリアルの狭間で立つ自身のセルフポートレイトの様でもある。
実際に、自身を撮り収めたカットも収録されているが、一貫して全てのカットに、菱沼の自身への叫びが写り宿っている。
“私を出して”
菱沼は、いわゆる社カメとして働く中、一週間程旅したジャマイカに魅了され会社を辞め再び数ヶ月滞在し、今まで向き合えなかった自身の得体の知れないモヤモヤに気づき、本作のLET ME OUTに辿り着いたという。
ジャマイカ滞在時に撮られた写真群が私は好きだ。
人の瞬時を愛でる様な、憑依するようなドキュメンタリズムを菱沼は持ち合わせている。
ここへもう一段高く飛んで戻る為にも、避けては通れない“自己喪失”が必要だったのではないかと思う。
都会で暮らし、現代社会のレールの上を歩いていると、時間は時を追うだけの“物”であり、食も生を補充するだけの“物”となり、全ての思考は、効率よくこなすだけの“物”へと向かう。
本シリーズは、その“物”化した得体の知れないモヤモヤを、写真という二次元に投影することで具現化し、それを留め、自己喪失へと向かう儀式にも似た、菱沼の写真行為だったのではないだろうか。
― Jeong Imhyang

井上青龍
『釜ヶ崎の子ども』
『京の都』
『ひとと石』
1960-1970年”釜ヶ崎”で、鮮烈に世に写真を轟かせた井上青龍。
今や伝説の写真家である。
“狼が抜き身で歩いているような男”は、釜ヶ崎に住みつきながら写真を撮り続けていた。当時の釜ヶ崎は暴動や喧嘩が絶えない地域であり“他者”が向けるレンズなど、争いの火種でしかなく、それ故、話合いや喧嘩にもなった。その果てに、人々と酒を飲むことで仲間が増えていったという。
「人間そのものが泣きたくなるほど好きになり、死んでしまいたいほど嫌いになる場所」
この言葉が、井上が暮らした釜ヶ崎の日々、人、街を物語る。
人を撮ることは自分を減らす。減らした分だけ人に写真が宿る。
ひとと石/京の都。
一貫として井上の人への慈愛が抜き身で歩いている。狼は、誠実さを隠すが故だったのではないだろうか。
釜ヶ崎以降井上は行き詰まり、長い空白時間を要した。
「結局、釜ヶ崎を変えることはできなかった。」
釜ヶ崎を撮ってから25年後、ようやく写真集が刊行され、井上は新たな撮影に挑んだが、南の海にさらわれ逝ってしまった。
人と誠実に向き合い、自身のジャーナリズムを信じ撮り減らした分、少し早い死期であった。
私は嘘がない写真を初めて見た気がした。
写真家である前に人間。
人間で生きることの本当の根底を、教えられたように思う。
井上が自分を減らして撮った分、今もなお、こうして、私たちに写真を宿してくれている。
― Jeong Imhyang



『香港好運』エリック
香港に生まれたEric。
Ericが香港を後にし、日本に来たのは、1997年香港が中国に返還された年だった。
国の未来への不安から、友人たちはカナダ、アメリカ、ヨーロッパへと向かった。
彼らの不安をよそに、Ericが国を出たのは“国際的家出”だった。
Ericの両親は中国出身だが、文化大革命の頃、香港に密入国し亡命した。
長い間自意識に災いされ、撮影することはなかった中国に2005年旅に出た。
本書は、Ericが中国でのスナップを撮りまとめた“中国好運”に継ぎ、香港に戻り真っ正面から香港と向き合い、撮影されたスナップ写真群である。
セットアップかと疑う程の至近距離。
人の心臓を斬り撮るような距離である。すれ違いざまに撮られた、1秒にも満たないその瞬間にその人の刹那を封じ込める。
その刹那は、写真でしか成り立たない、写真にしか存在しない“時間”を生け捕る。
その時間は、人が持つ本質的エナジーを爆発させ、あっという間に視覚から心に触れとてつもない速さで体からすり抜けて行く。
まるでカマイタチの様に。
個と群衆、情勢蠢く2019年、香港。
ここにある、香港を、人々を、自由を切に願う。
この本質的エナジーに、再び出会いたい。
― Jeong Imhyang

『1973 中国』北井一夫
日本の闘争の歴史の重要な局面にカメラを向け、社会と写真への反抗として世に写真集という形で示した“抵抗”だったが、時代の流れと共に左翼急進主義は変貌し、北井のプロテストとは大きくかけ離れていった。
左翼急進主義に幻滅した北井の視線は、農村の生活へと向かうようになった。
その中、1973年木村伊兵衛より自身のルーツでもある中国への旅の誘いを受け同行した。
本書は、その時に撮られ記録されたモノクロームの写真群である。
1973年の中国は共産党政権が24年を迎え、文化大革命7年目の年にあたる。
外部とは遮断され、混乱と内部抗争に揺れる激動期であったが、北井写真に写るは、人々の穏やかな日常である。
カメラという“異物”に違和感を覚えながらも、好奇心に満ちた顔でレンズを覗きこむ人々。卓球やアコーディオンに勤しむ子供。荷台に子供を乗せている老婆。
印象的なのは、北井のレンズに笑顔を向ける人々の顔である。
北井は日本の敗戦の8ヶ月前、1944年に旧満州鞍山市で生まれた。
日本帰国時はまだ1歳未満であったが、北井にとってこの旅は、失われた幼児体験の過去を喚起する旅となった。
生地や血のルーツは、意識の中に漠然とどこか、少し重い暗さを帯び育つ。
幼児期の記憶は残らないというが、母から聞いていた中国は、自身のルーツの記憶として知らぬ間に“失われた幼児体験”として、北井の意識に記憶されていた。
中国への旅先の風景に自身の幼少期の姿を探し、失われた記憶に心を重ねたのは、家族の苦しみの中にもあったであろう希望と幸福の記憶を見たかったからではないだろ
うか。
そのことが、激動期にいる人々の笑顔を誘引したのではないかと私は思う。
― Jeong Imhyang
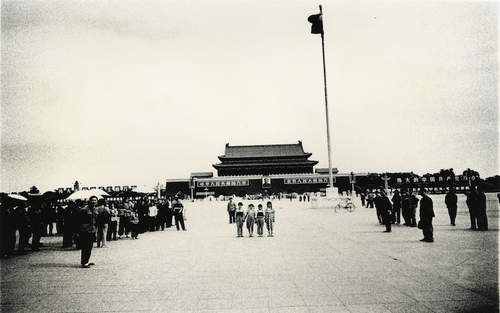
『涅槃の谷』山縣勉
涅槃。
<一切の煩悩から解脱した、不生不滅の高い境地。転じて、釈迦や聖者の死。入滅。>
本書は、山縣の父が癌を患い、その治療方法を調べるうちに辿り着いた、癌治癒のために集う東北の谷を撮り収めたものである。
湯治は日本に古くから存在する治療法である。中でも、癌治療に効力がある放射性元素を含む北投石が産出されるのは、日本ではこの谷だけである。
その石から放たれる放射線の効力を求め、人々は山を中心に横たわる。
山縣はその光景を初めて見た時、涅槃図を思い出したという。
癌は今では、現代の医療の進歩に伴い、死が近い病ではなくなろうとしている。
しかし、患った年や性別、癌細胞がある臓器の場所によっては、とても厳しい治療や手術を伴い、死を予感させる。
予感は人々を、魂の療養ともなる湯治場に向かわせる。湯治場はその人々の生と死を受容し、ただそこに存在し続ける。
沸騰し流れる川。
湧き上がる煙。
転げ繋がるように点在する岩。
人々の祈るような思いが、モノクロームに静かに咽び定着する。
撮る行為とは、その光景に添うことでもある。
“安寧の世界への準備と循環する生”と、記す山縣はその光景に添い何を見たのであろうか。
厳しい治療を経て、緩和への道を探り、人々がその谷に足を向けたことは、涅槃とは裏腹に生への渇望であり、捨てることなき生への希望であると私は思う。
祈りが定着したモノクロームの先を、今一度山縣に問いたい。
― Jeong Imhyang

『香港』山内道雄
中国返還直前の香港。
本書は、1995-1997年にかけて山内が2、3度渡航を繰り返し訪れ、時代の波に蠢く香港を撮らえた写真群である。
街の狂熱がモノクロームにざわめく。
情勢と共に歩んだ、混沌とした街のエナジーが、山内の撮らえる視覚を加速する。
飢え空かせた腹を満たすよう、貪り食べるように、街を撮り尽くしていく。
スナップ写真が持つ秩序と無秩序が、香港の秩序と無秩序に綯交じる。
山内特有の距離は、貪欲な写欲とはうらはらに、しゃなりしゃなりと身をこなし、人々の顔、路上に近づいては離れ、街のエナジーを可視化していく。
なぜ、スナップなのか?
なぜ、街なのか?
数え切れないぐらいのスナップ写真に遭遇する。
その度に浮かぶ答えは、正解であり不正解なのだと、山内写真が嘲笑う。
人間の本能で撮らえる写真に、答えなど存在しない。
答えが見えたらとっくに、写真を撮ることを終わらせているだろう。
街を彷徨い、路上を歩き回り、生きている”生”を探し、腹が満たされるまで撮り続ける。
撮り切られた街は、山内の見た香港であり、それ以上でもそれ以下でもない。
そのことは、写真に向き合う山内の誠実さと、ある種ニヒリスティックさをも合わせ�